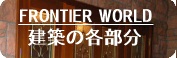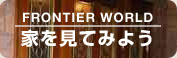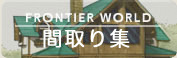モーリス 第5回 由美子さんとの出会い

九州で行われた弓道の世界選手権で、モーリスは
由美子さんと 出会う。
合気道仲間のもつ古い家に住むことになったそのまま
では住めない。いろいろ改造しなくてはならない。
なんといってもまずは 水の確保の問題。
300mはなれたところに水量の安定した渓流が流れているあれを何とか利用できないか。
しかし300m近く離れ、しかも20m以上低い位置にある。
それを持ち上げて運ばければならない
モーリスはハイドロラムというシステムにトライする
ことにした。日本ではその例が見つからない。
由美子さんと 出会う。
合気道仲間のもつ古い家に住むことになったそのまま
では住めない。いろいろ改造しなくてはならない。
なんといってもまずは 水の確保の問題。
300mはなれたところに水量の安定した渓流が流れているあれを何とか利用できないか。
しかし300m近く離れ、しかも20m以上低い位置にある。
それを持ち上げて運ばければならない
モーリスはハイドロラムというシステムにトライする
ことにした。日本ではその例が見つからない。
第1回 雪崩からの奇跡の生還
第2回 生い立ち
第3回 バンクーバー島の旅
第4回 合気道修行時代
第5回 由美子さんとの出会い
第6回 家の改造大作戦
第7回(最終回)家の完成そして二人の結婚
第5回 目次
※番号をクリック→希望の項目に飛ぶ
1序:固唾を呑む瞬間
果たして水は出るのだろうかと由美子さんが固唾を呑んで見守るなかで、モーリスはバルブを開けようとしていた。
もし出ないと、これまで二人でやってきた苦労は、それこそ水の泡、出ると信じたい、だけど・・・ 動力を一切用いずに、水の落差エネルギーだけを巧みに利用して水を送り上げる「ハイドロ・ラム」というシステムで、かなり昔に発明され、低開発国では結構使われている方法だという。それが本当だとするとランニングコストはゼロになるが、そんな上手い話が本当にあるのだろうか。
大家の鈴木さんや水道屋さんが時々見にきては、そんなの上手くいくわけはない、無駄なことをして気の毒にという顔をして帰っていく。 その原理を説明してもらい、2mくらいの高さで水が上がるのは確かに見た。しかしこんな簡単な装置で20mもの高さを持ち上げるとなると、どうしても信じられない。 今日はこれから中間点のテストをする。中間点といっても落差10m以上ある、かなりの高さだ。
祈る気持ちの由美子さん。(出るにきまっているさ)自信たっぷりに、モーリスはバルブを捻った
2出会いは世界弓道大会

モーリスが由美子さんと出会ったのは、1999年3月、初来日から5年目の事だった。宮崎県の都城市、ここで第三回世界弓道選手権が開かれ、当時弓道3段だったモーリスは講習会と昇段テストを受け4段に合格、引き続いてこの試合に参加した。
旅行会社のJTBに務めていた由美子さんは、事務局のスタッフの一員として働いていた。 「成績は?」と聞くとモーリスは笑ってこたえない。「試合となるとモーリスは緊張してしまうみたい」と代わりに由美子さん。それをキッカケにモーリスと由美子さんの付き合いが始まり、紆余曲折を経て、モーリスは真剣に由美子さんとの結婚を考えるようになる。
所帯をもつとなると、今住んでいる家より、もう少し広い家に住みたい。道場に通うには便利だが周囲に家が建て混んでいて落ち着かないし景観もよくない。二人であちこちと探し回ったが、適当な家がなかなか見つからない。
そうこうしているうちに、合気道を通じて知り合った稲垣さんが、昔自分が作った家があり、今空いているから使ったらどうか言ってくれた。土地の持ち主である鈴木さんもやはり合気道仲間である。
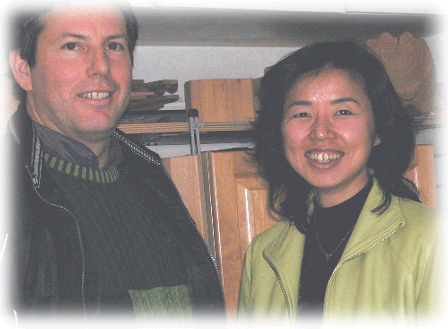
モーリスと由美子さん(私の事務所にて) 「先週ガールフレンドが来て住む家を一緒に探したが、良い家を見つけた。素晴らしく景色のよい場所だ。問題は家の改造に大分手間がかかりそうなこと。大工道具は全てカナダにおいてあるし・・・」
モーリスからそんな手紙が来たのは2001年10月の事だった。ガールフレンドというのが今思うと由美子さんのことだ。 山中にひっそりとたたずみ、周囲に人家がない。標高220mほどに位置し、はるか遠くに太平洋を望める素晴らしい景観。南に530mほどの山を背負い緑に囲まれている。二人は一目でその場所が気に入った。建てられたのが26年前、大分痛んでいるが、修理をすれば何とか住めそうだった。
そこから二人の家作りの苦労物語が始まる。
3..善意の人々との幸運な出会い
稲垣さんはボランティア精神に溢れた素晴らしい人格者だと、後に由美子さんが手紙で教えてくれた。ミヤンマーに合気道道場を作り、毎年数回指導にいくという。土地のオーナーである鈴木さんはその稲垣さんの合気道の後輩である。 鈴木家に二人で訪問し、家を借りたいと申しいれると快諾してくれたばかりではなく「改修工事をしたい」とモーリスがいうと早速工具置き場に連れていってくれた。
鈴木家に二人で訪問し、家を借りたいと申しいれると快諾してくれたばかりではなく「改修工事をしたい」とモーリスがいうと早速工具置き場に連れていってくれた。由美子さんが待っていると、モーリスは信じられないというような顔で戻ってきた。
「何でも揃っているんだ、まるでクリスマスと正月がいっぺんに来たような気分」と目を輝かせて由美子さんにいう。好都合なことに鈴木さんは工務店を経営しているのだった。
鈴木さんは会うといつも冗談を言っては二人を笑わせ楽しませてくれる。 写真:広い庭の先に遠く太平洋を望む素晴らしい景観
モーリスはジョークの通じる友人が出来たと喜んだ。二人は鈴木家の人々
と家族ぐるみの親しい関係を築いていく。
「稲垣家、鈴木家の皆さんがいなかったら、大げさではなく、今の私たちはなかったと思います」
モーリスと由美子さんにとっては、善意にあふれた人たちとの幸運な出会いである。
4.ハイドロ・ラム
家の改造に入る前にまず解決しなければならなかったのが水の問題だった。井戸を掘れば良いのだが、お金は掛けられない。
離れたところに沢が走り、安定した水量がある。モーリスは前から興味を持っていた「ハイドロ・ラム」のシステムを取り入れることにした。 しかし色々調べたが、日本では全く知られていず必要な部品はどこにも売られていない。モーリスはメカニシャンである。それなら自分で作ってみようと考えた。
まずインターネットで情報を集め、このシステムの原理や、機構を研究した。次に必要な部品をリストアップし寸法や形や必要な数量を計算する。 それぞれのパーツは似たような物をかき集めれば何とかなるだろう。
沢を歩き、場所を決める。そこから家までの距離は270m。家と水 源の落差を測ると凡そ20m。20m上に水を送り上げるには、高さ3mほどのダムが必要と計算した。

DIY店や金物屋、水道設備の店、色々なところを探し回って部品を集めた。それを組み合わせ、装置と全体のシステムを作っていく。
装置の主要部のair vessel(ボンベのような形をしている)の本体は異なる径の塩ビ管を組み合わせて作った。しかし肝腎な部品がひとつ見つからない。 それが手に入らなければ、計画を諦める他ない。かなり遠くまで足を伸ばし散々探しまわったが、どうしても見つからない。
こんな小さな店にある訳ないなと思いながら、最後に地元の小さな金物屋にはいった。店主と一緒にごそごそと倉庫を探すと「あった!」。 小躍りしたい思いだった。「信じられなかったね。本当に嬉しかった。」
装置が完成し続いて工事に着手。
まず岩や石を集め、上手く組み合わせながら積んでいき、落差3mのダムをつくり本体と塩ビ管でつなぐ。
家までの270mもの距離を配管しなくてはならないが、幸い廃業した豚舎が近くにあり、不要になった直径35mmほどの鉄のパイプを分けて貰えた。
30cmほどの深さに溝を掘り鉄のパイプを埋め、その中にビニールのパイプを通していく。地中に埋めるのは凍結を防ぐためだ。 最初の急斜面が大変だった。笹が繁茂し、根をはっている。スコップや鍬で溝を掘り進める。 うまくいくのだろうかという不安を拭えないまま、由美子さんも一緒に汗と泥にまみれながら手伝う。
5.水が出た
さあ、いよいよテストだ。ボンベ本体のコックを開ける。圧縮された空気の圧力で爆発的に水を押し出す時の、カーン、カーンという独特の音が一定の間隔で始まる。モーリスと由美子さんは水管の先へと向かう。半信半疑で由美子さんが見守る中で、モーリスがバルブを開けた次の瞬間、シュッツ、シュっと、間歇的に水が噴出し始めた。
「由美子が、はっと息を呑むのが分かった。えっ、本当、まさか?という感じだった。出るとは信じられなかったのだろうね」とモーリスは可笑しそうに笑った。
写真:モーリスはハイドロラムの説明をしてくれた

残り150mほどを配管しなくてはならないが、水が出るという確信を得て由美子さんも張り合いがある。
竹や雑木や草が根を張り巡らす地面を掘り管を埋め、土を被せて戻す。雨の日はずぶぬれになり、晴れた日は強烈な太陽に焼かれ、黙々と二人で作業を続け家まで配管し終えた。
部品探しから始まり、2ヶ月ほどかけて工事が終わり水供給のシステムは完成した。